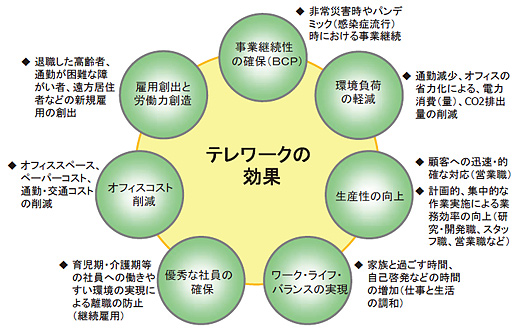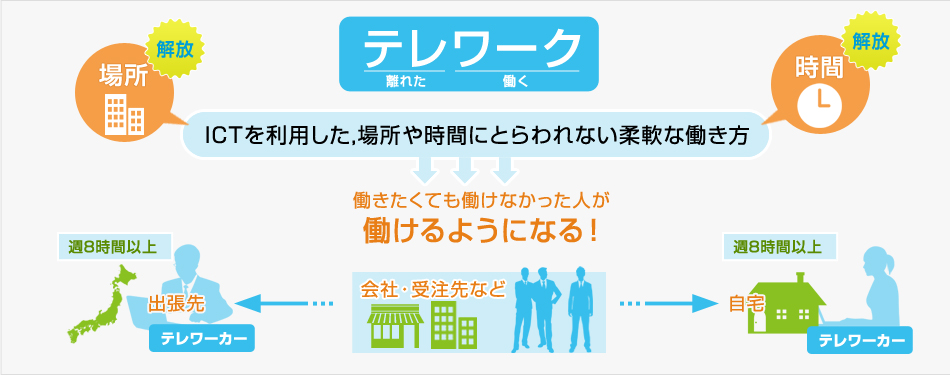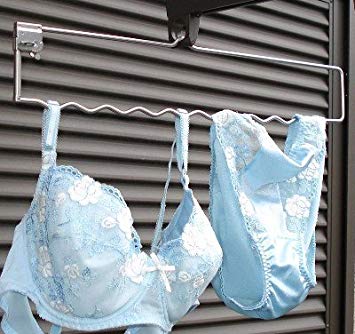「ミクシィはコミュニケーション屋である」木村こうき新社長に聞く事業戦略 日本におけるSNSの先駆けとしてその名を知らしめた「mixi(ミクシィ)」。2013年半ばまではSNSの会社だったが、今ではゲームアプリ「モンスターストライク」関連で全社売上高の9割以上を占めるゲーム企業に成長した。モンストの勢いにも陰りが見えるなか、次の一手は? 6月に新社長に就任した木村こうき氏(42)に、今後の事業戦略を聞いた。スポーツとウェルネスの両分野で新規事業──ミクシィの強みは? 木村 私たちは自らを、SNS屋でもゲーム屋でもなく、コミュニケーション屋と定義しています。SNSは、離れた人とコミュニケーションできるサービスであり、モンストも1人ではなく、複数の人が対面で遊ぶゲームです。これらで培ったノウハウや技術、従業員の高いモチベーションが強みであり、他社との大きな差別化のポイントです。── 商標法違反などの問題を受け、5月にチケット売買仲介サイト「チケットキャンプ」を閉鎖しました。どのような影響が出ましたか木村 社内では、コンプライアンスとレピュテーションリスクへの意識が高まっています。組織面でも、執行役員制を導入するなど体制を強化しました。チケットキャンプは、チケットの高額転売が問題視されるなど、批判も多い事業でした。今後は、皆さまの声によく耳を傾け、喜ばれるサービスだけを徹底してやっていこう、と肝に銘じています。 |