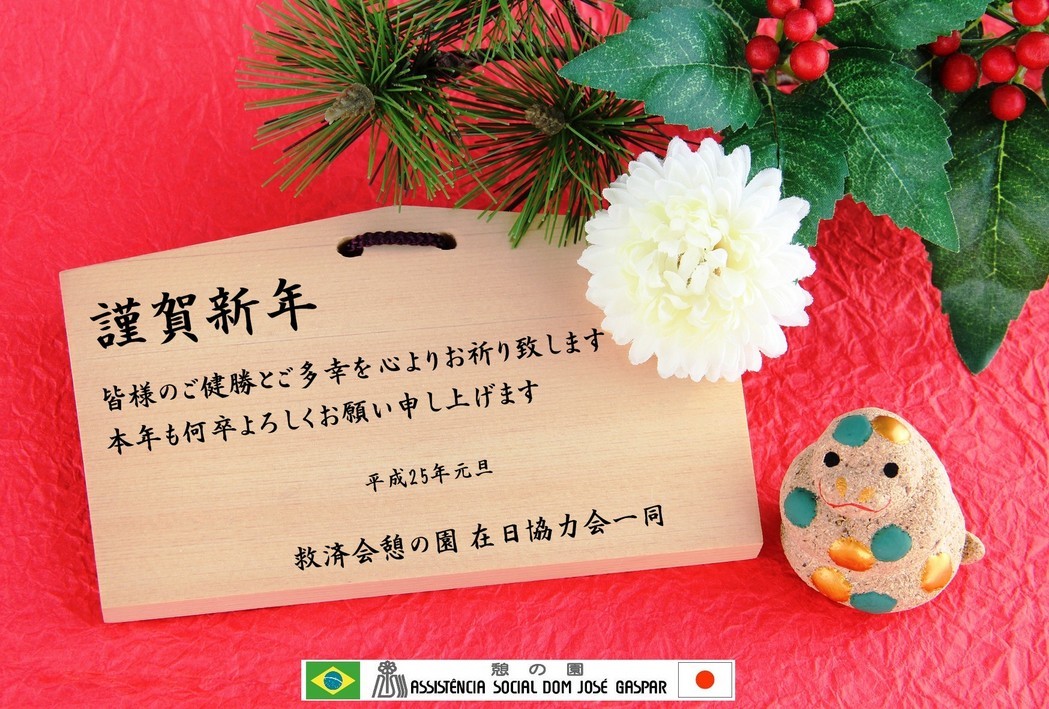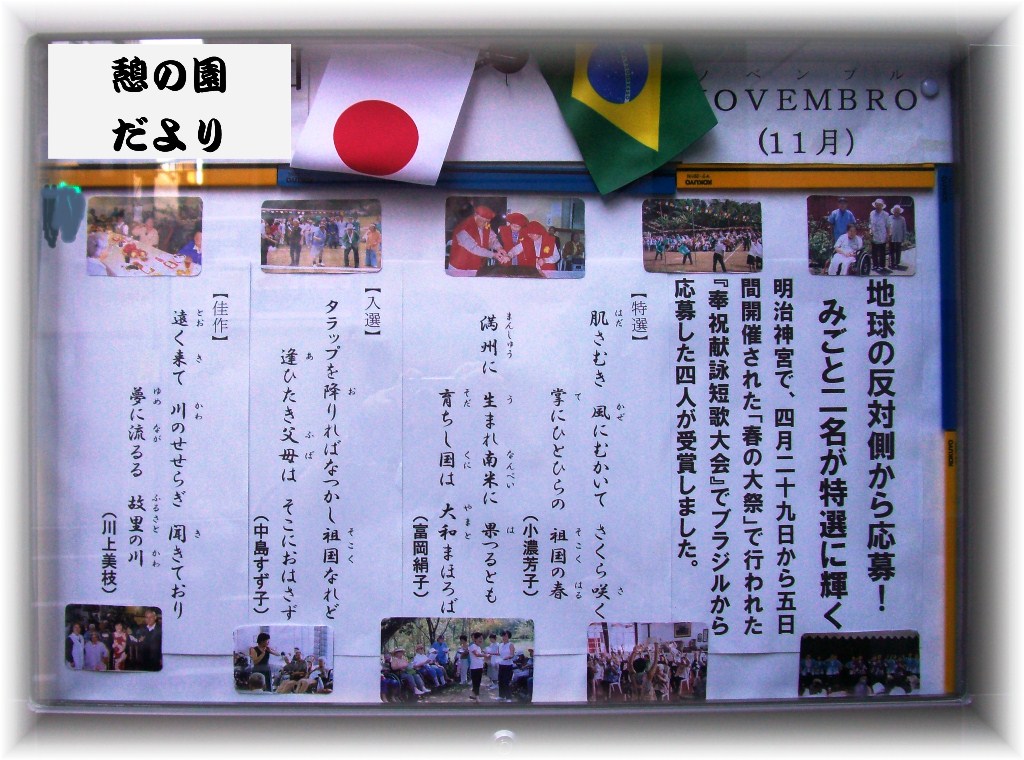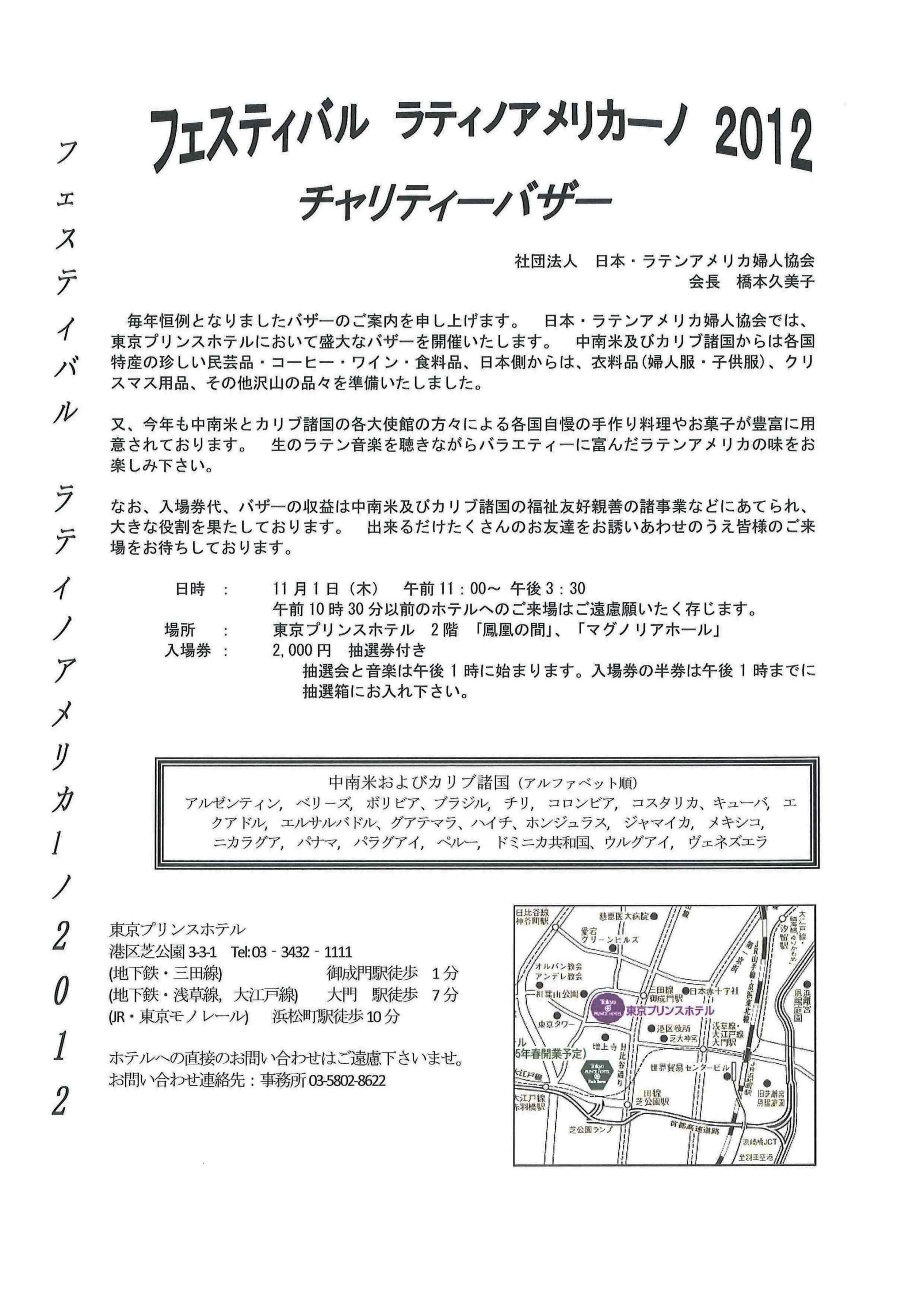リオグランデ・ド・スル(Estado de Rio Grande do Sul)は、
ブラジル最南端に位置する州で、西にアルゼンチン、
南にウルグアイに接し、東は大西洋に面しています。
亜熱帯性気候ですが、比較的顕著な四季があり、
降水量は1年を通して均等にありますが、旱魃が起きることもあります。
冬は山間部で雪が降ることがあり、雪が降ると観光客が
集まるそうです。雪はブラジル人には珍しいのですね。
夏は30℃まで上昇して、日射病にかかることもあるそうです。
ドイツ系とイタリア系の移民も多く住んでいて、それぞれの文化を
大切に継承しています。
12月はクリスマスのデコレーションが町のあちこちに見られ、
チョコレート工場ではチョコレートで作ったサンタクロースが
工場を訪れるお客さんを甘い香りで出迎えてくれます。
イタリア系移民のブドウ畑に囲まれたワイン工場では、
ワイン醸造の過程が見学でき、もちろん試飲できます。
試飲のあとは多くのお客さんがお土産に買い求めます。
それが工場の狙いですが・・・
また、併設されているレストランでは音楽を聴きながら、
ワインと料理を楽しむことができます。
観光用の薪で走る機関車は迫力十分です。
車内では狭い通路で、アコーディオンに合わせて歌って、踊って、
楽しく過ごすのがブラジル流旅行術です。
ブラジルの南部の州の至る所に生えているのがパラナ松です。
松の一種かと思いますが、ナンヨウ杉の一種で建築材や
パルプ材等に利用されます。 形がちょっと変わっていますね。
大きなボールのような実をつけ、その中に細長い種が入っていて、
塩で湯がくと少し栗のような味がします。
「ブラジルの南部で雪が降る」
緯度から見れば不思議なことではないですが、
「雪が降った!」と雪見観光に出かけるブラジル人、
想像すると何となくおかしくなりませんか。
<H.Takahashi>