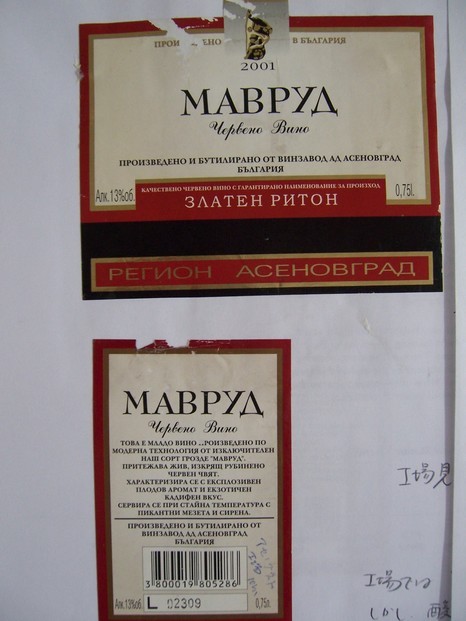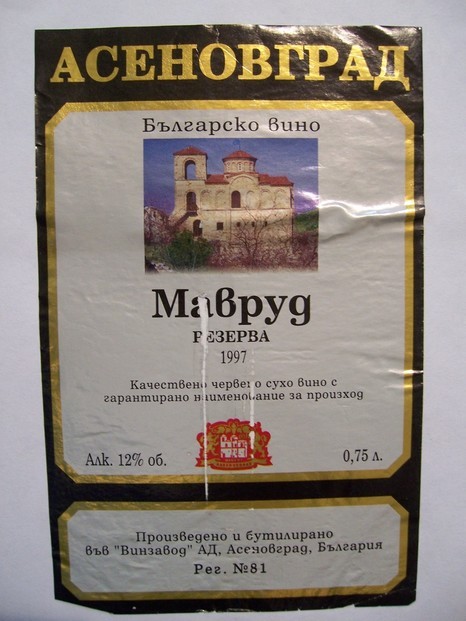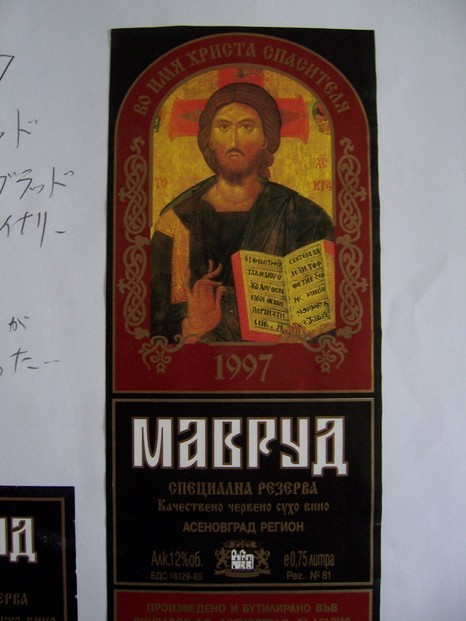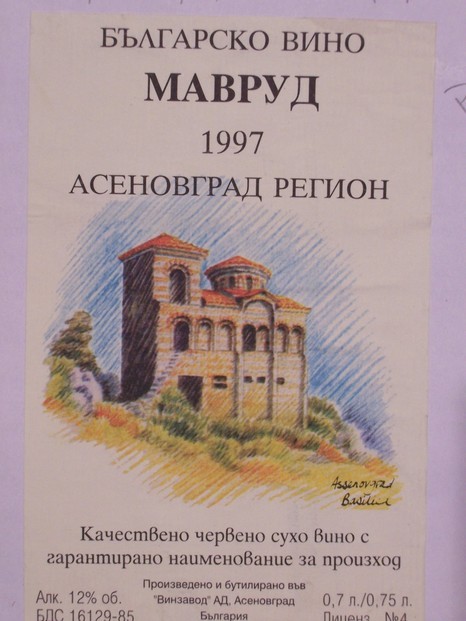今日は、久しぶりに「ブルのあいうえをシリーズ」に戻ります。ええつと〜、順番では、「て」でしたねえ・・・。「ブルのワインシリーズ」もこれで終了ではなく継続しますので、ご心配なく。
○鉄道(てつどう)の踏切
ブルの踏切の傍らをよく見ると、小屋が建っていることがあります。小屋といっても、人が住むことができるような大きさです。ここからは確かな話ではないですが、この小屋に人が住んで、踏切の遮断機の上げ下ろしを行う人が住んでいるのです。
私も地方に行って2〜3回遭遇したのですが、めったにブルの踏切で列車の通過待ちには会わないのですが、最初に警報機の音が鳴り出し、おもむろにその小屋から太ったおばさんが出てきて、丸い取っ手をぐるぐる回し、遮断機の上げ下げをするのです。列車がくるかなり前から遮断機が降りて、再び車が通過できるまで、出店が出て、飲み物・スナックが売られているという光景まではないですが、時はゆっくり過ぎていく感じです。ようやく、列車(あえて、電車とも汽車とも言いません)が通過し、太ったおばさんが再びその小屋から出てきて、取っ手を回して車が通過できるようになります。
その小屋がおばさんの棲み家であると確信したのは、踏切を通過しその小屋の横で、そのあばさんが洗濯物や布団を干していたからです。
写真は、踏切を通過するブルの列車です。マダラの壁画に行く道中です。
○電気(でんき)の話
ブルの電気料金は、EU加盟までにどんどん値上げです。これまでも毎年のごとく値上げされていますが、10月には6.9%の値上げ。来年の夏には、今年末にコズロドゥイというところの原子力発電所の2つの原子炉が閉鎖することに伴って、少なくとも10%の値上げが見込まれているようです。
ちなみに、この原子力発電所は、6つの原子炉がありましたが、そのうち4つがあのチェリノブイリの原子炉と同じ型ということで、EU加盟の条件として、6つの原子炉のうち4つについて廃止を求められ、既に2つの原子炉は閉鎖されています。
ブル国内の発電電力量のうち、約42%が原子力発電によるもので、原発の閉鎖によってこれまで周辺国に電力を輸出しえいたのですが、来年からギリシャ、トルコ、セルビア、マケドニア、アルバニアへの電力輸出を停止すると発表しています。
写真は、原発とは全く違いますが、ブルに日本の電気製品などもっていくときの必需品である、変圧器です。これはせいぜい、100Wくらいまでの出力に対応するもので、炊飯器のような1kwクラスのものに対応するには、もっと大きな5〜7kgもの重さのものになります。