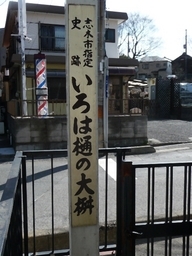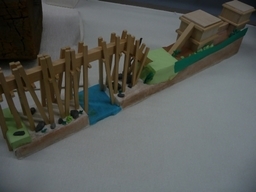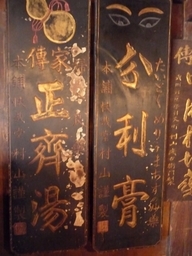2011/03/04 10:22:11�b���ƍ����Ƌ� |
���Ȃ�x�����Ēn��ɏo�Ă���l�Y�~ |
2011/03/03 7:53:18�b���j�̊X���� |
�u����͔�̑喑�v�s�j�� |
2011/03/01 21:34:07�b���j�̊X���� |
�u�؎s�@�����ӂ̐��ˁi�݂Â��j--�M�d�ȕ����� |
2011/02/28 19:16:31�b���j�̊X���� |
�����B�Ƃ̋����R���Ɠ� |
2011/02/27 9:37:08�b���̑� |
�u�؎s�������u�����R���Ɠ��v |